社会の中でそれなりに歳を重ねてきたこともあり、職場などで後輩に悩みを相談されたり愚痴というには少し軽すぎる悲痛な叫びを聞いてほしいとお願いされることがあります。自分自身ももちろん彼ら彼女らの年代の時は同じように悩み苦しんだことがあったわけですが、今になってあの時自分はどうやってやり過ごしてきたのか、あくまで1つの例として後輩に伝える2つのことがあります。今回はその2つについてご紹介したいと思います。
1.2-6-2の法則
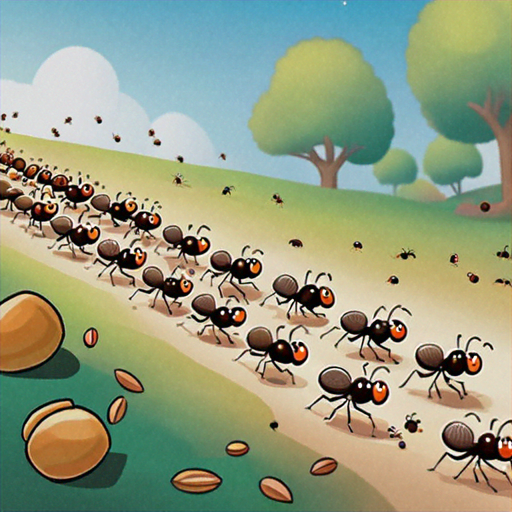
働き蟻を例にとりチームビルディングや組織論などの本にもよく出てくる法則ですが、実は人間関係にもよく当てはまることが知られています。私がこの法則を初めて知ったのは垣根涼介さんの「信長の定理(上・下)」(角川文庫)という小説を読んでからなのですが、自分にとっては何とも腑に落ちる法則でした。(この書籍自体は歴史に絡めたお話で大変お勧めです)
私にとって、あなたにとって、自らが属する職場やコミュニティの中で特に親密で信頼できる相手は全体の2割、時々連絡を取ったりはするが特別深いわけでもなく自分の日々の思考や感情の起伏に大きな影響を及ぼさない相手が6割、時に対立したりなんとも苦手でどうも分かり合えない気がする相手が2割。いかがでしょう。職場やチームなどを1つの単位として想像してみるとなんとなく2-6-2に分かれるような気がしませんか?
ここで思うに大切なことは、
・必ず苦手な相手は一定数いる
・だけど味方になってくれる信頼できる相手も一定数いる
ということだと思います。
苦手な相手を排除するのではなく相手や相手の考え方は多様であり人間関係ってそういうものなのだと認識することがとても大切だし、人間関係でなにか嫌なことや落ち込むことがあっても少し気楽になるのではないかと思います。
2.エネルギー保存の法則

物理の授業などで出てくる言わずと知れた物理学における保存則です。熱力学の分野では熱力学第1法則として知られ、ある系において生成されるエネルギーと消費されるエネルギーは同じ、ということで平たく言うとプラスマイナスゼロ、ということです。現代物理学においては、実は我々がいる宇宙もビッグバンと呼ばれる大爆発から始まったとされていますがその前は無(ゼロ)の状態であり、無から生まれて膨張をつづける宇宙はいずれ収縮しやがて無に戻る、という説が有力です。
宇宙に例えると壮大すぎるかもしれますが、考えると我々人間もゼロから生まれてやがてゼロになります。つまり結局プラスマイナスゼロなのだと私は思っています。その過程において、いいこと(プラスのエネルギー)もあればいやなこと(マイナスのエネルギー)もあるし、決して悪いことばかり続かないんだと思います。自分以外の他人も自分にプラスのエネルギーを与えてくれる人もいれば、エネルギーを奪っていく人もいる。考えが似ていている人もいれば異なる考えの人もいる。そう思えると少し楽になるのではないかなと思います。
何かとストレスが多い現代社会、レジリエンス(心理的回復力)の大切さが言われていますがこのような相手の多様性をそういうものなのだと認識して受け入れていく力もますます求められてくるのではと改めて感じました。皆さんが皆さんそれぞれ何かを考えるきっかけになって頂けると幸いです。


